 本書は欧州の通貨政策という視点から、戦後日本が何をしてこなかったか?を明らかにした本である。舞台はインターナショナルだが、筆者の日本に対する思いがあちこちに感じられる本でもある。
本書は欧州の通貨政策という視点から、戦後日本が何をしてこなかったか?を明らかにした本である。舞台はインターナショナルだが、筆者の日本に対する思いがあちこちに感じられる本でもある。
言うまでもなく、98年ユーロ誕生に至る通貨統合は欧州統合運動の核心であるが、本書は視野を通貨に限定していない。20年代の汎ヨーロッパ主義の誕生から説き起こし、戦後の独仏が歴史の清算を経て運命共同体を形成していく様、そしてEECから単一欧州議定書(87年)によるヒト、モノ、サービス、資本の域内自由化と通貨統合の関わり、更にはマーストリヒト条約後の欧州政治システムの統合と分権化までを含めた欧州統合の全体像を平易に、かつ、学際的に解説している点が貴重な一冊でもある。
18世紀以降の欧州のバランス・オブ・パワーに多くの紙面を費やしたキッシンジャーの大著「外交」(日本語版 岡崎久彦監訳 96年、日経新聞社)は、不知のせいか故意に拠るものか、この欧州統合を殆ど黙殺している。日本でも学界といわず、論壇といわずアングロ・サクソン世界観のバイアスが強いせいで、欧州のこの壮大な歴史的実験のことは意外と詳細には知られていない。しかし、そこには確かに今日の日本、そして東アジアが汲むべき教訓が含まれているというのが読後の第一感である。
政治に関しては、二つのドラマが印象に残った。第一は第二次大戦の傷跡も生々しい1950年、「16世紀以降27回にものぼる戦争」を繰り返してきた独仏両国が歴史的和解への一歩を踏み出したことだ。争奪・抗争が繰り返された独仏国境地帯の石炭・鉄鋼産業を両国の共同管理下に置くことを提唱した「シューマン・プラン」が欧州石炭鉄鋼共同体の誕生(1952年)につながっていく。
もう一つのドラマはベルリンの壁崩壊直後、1990年に行われたコール/ミッテランによる独仏首脳会談の密約であろう。「(長い間欧州の悪夢であった)統一ドイツを容認する代わりに・・・統一通貨(EMU、後のユーロ)を誕生させることによって、そのドイツをヨーロッパの中にからめ取る」壮大な取引だ。
ドイツはかつて第一次大戦後に経験した天文学的インフレを教訓として強い通貨をめざし、80年代には欧州基軸通貨国の地位を確立していた国だ。マルクを捨てることは一大決断を要したに違いないが、この取引によってドイツ統一への祝福だけでなく、統一通貨の諸制度を「実質的にはほぼドイツの思惑通り」に決める力も得たのだ。
著者は「何よりも関係国の政治的な意志の強さこそが統合の推進力」だったと言う。ドラマの影にはビジョンを持つ偉大な政治家、賢人たちがいた。真の政治とは何か、何をなしうるものか、を教えてくれる。
本書の核心、通貨統合に至る道のりの解説はかなり専門的な部分だが、遠大な戦略を描き、その実現のために弛まず努力してきた欧州の姿が印象深い。
欧州は、米国が突如金・ドルの兌換を停止し戦後のブレトンウッズ体制を一方的に崩壊させた1971年のニクソン・ショックの翌年から、98年ユーロが誕生するまで、四半世紀以上にわたって域内固定相場制を続けた。この間、欧州は年中行事のような平価調整や累次の参加通貨の危機に遭遇しながらも固定相場制を発展・深化させつづけたのだ。
為替安定のためには各国が金利引き下げ、財政出動など通貨を弱くするマクロ経済運営を自制し、協調行動をとらなければならない。不人気な政策で各国が歩調を合わせたのは、国際収支管理に責任を負わないばかりか、ときにドル安誘導まで平気で行うようになった米国を見て「ドル中心体制の黙認は有害」であると悟ったからだ。弱い欧州が強い米国に対抗するためには団結しなければならない。そう考えれば通貨統合への道は必然だった。
日本も累次の「急激な円高」に苦しんできたが、変動相場制は全くの「与件」であった。これに対して、西ドイツは急激なマルク高/ドル安に直面して「重荷をもっと広い地域に拡散」し、「他の欧州諸国にもその負担を分担してもらいたい」と考えたのだ。欧州を鏡にすると、まさに日本は何をしてこなかったかが見えてくる。
日本は85年のプラザ合意で決まった為替調整の達成後も一向に下げ止まらないドルとのシーソー・ゲームに翻弄され、欧米を協調介入に引き込む見返りとして空前の金融緩和を行い(87年ルーブル合意の頃)、平成バブルの引き金を引く・・・。次には金融引き締めで逆の極端に走り、バブル崩壊後の「失われた十年」が来た。あげくに98年のアジア経済危機のときには円と日本株に大規模な空売り投機をしかけられて長銀破綻に象徴される窮状を招いた。
一連の通貨政策がどれほど日本の国益を損なった(あるいは護り損なった)ことか・・・。最近の通貨の研究にはこの点を痛恨事とするものが少なからずある。「マネー敗戦」(吉川元忠著、98年文春新書)もそうだった。また、「ドルと円」(D・マッキノン・大野建一共著、98年日経新聞社)は、「貿易収支不均衡は為替で調整できる」という根拠なき信念と長年の日米貿易摩擦が「円は下がらない」という長期的予測(円高シンドローム)を生み、これが企業経営に決定的に重要な価格シグナル(生産投資に必要な予測可能性)を乱し、日米双方の経済厚生を傷つけたことを論証した。
著者もこの経験でトラウマを負ったことだろうが、必ずしも米国に「怨念」を向けようとはしていない。なぜなら、そういう目に遭わないための自衛策をとってきた欧州の先例があるからだ。日本はこの点で確実に何かが欠けていた。もちろん、近隣との関係ひとつとっても、欧州に通貨統合なさしめた環境条件が日本に備わっていた訳ではないが、そうだとしても、人を恨む前にこの点を反省すべきだろう。
さて、著者は以上のような欧州の経験を紹介した上で、東アジアが汲むべき教訓を提言している。上記から明らかなように、本書の影の主役は、圧倒的な基軸通貨国米国である。東アジアも「アメリカ離れ」して団結し、共通の通貨制度として「日本を除く・・・東アジア諸国が円、ドル、ユーロの3極通貨バスケット・ベースの固定為替相場制を採用することから始める」べきと主張する。また、東アジア統合推進のためには「日中が共同してリーダーシップを発揮していく」べきであり、そのために「日本はアジアの中で生きることを決意し」、「ヨーロッパにおけるドイツの役割を果たすべき」であると訴える。あまたの親米・恐米派は聞いただけで顔色が変わりそうな中身だ。経済から出発して、これほど正面切って「日中枢軸」を提唱した本は恐らく類例がない。
ヨーロッパ通貨統合から得られるレッスンはそういうことだ。貿易通商の地域統合と通貨の地域統合には大きな違いが一つある。前者には東アジアだけで統合し、米国を排除する畢竟の理由がない。あるのはただ、米国とFTAを締結するにしても、まず東アジアで団結して、交渉力を高めた上で行うべき、といった戦術論だ(実際、そうしないかぎり、交渉の中で米国の歪曲的なアンチダンピング政策の修正を求めることなど及びもつかないだろう。いま、まさにラテン・アメリカがFTAA((南北)アメリカ自由貿易協定))の交渉の中でそういう駆け引きをしている)。
これに対して、通貨の地域統合は規律の欠けた基軸通貨、ドルに振り回されないための仕掛けだから、アメリカを入れたら意味がなくなる。したがって、通貨統合の観点からは「東アジアは『アメリカ離れ』して、東アジアで団結すべき」ことは論理的帰結だ。
しかし、グランドデザインはそうだとしても、問題はそこに至るエンジニアリング(詳細設計)だ。いまのYenの責任者は通貨について、近隣当局との信頼醸成どころか、円安誘導の口先介入と「人民元が安すぎる」話しかしない。日本が目下の経済低迷をまず脱却しないと、アジア統一通貨は遠くなるばかりだ。
未だに選挙区に公共工事を斡旋することしか考えない政治家にも、長期的国益から見た通貨統合の重要性を理解させる必要がある。毎度々々景気対策の補正予算を求める政治風土から見て、財政規律がなぜ必要か等、理屈の説明から難航するだろうが。
それにもまして難しいのは、「日米中」の三極関係だ。決然と日中枢軸を説いた著者の勇気を買うが、率直に言って、評者(津上)はそれほど楽観的になることができない。米国が黙っていないだろう、などと腰抜けなことを言いたい訳ではない。
名うての「親中派」の評者でも、いま直ちに「米国を取るか、中国を取るか」の厳格な二者択一を迫られれば、躊躇なく米国を取る。未清算のままの歴史の瘢痕、体制の相違、悲しいまでに低水準な相互理解・・・いまの日中関係は深い相互不信に覆われている。
本書は日中両国が独仏の歴史的和解から教訓を汲むべきことを教えてくれる。筆者も日本は歴史問題についてはし残している仕事が多々あると考える。しかし、中国のことわざ「拍手は片手ではできない」のとおり、歴史問題の解決も日本だけの努力ではいかんともし難い。中国も学校で教える日本が否定的評価に極端に偏っている。おかげで中国の若者は半数以上が「日本は嫌い」と明言する有様だ。
日中双方は歴史的和解について、まだまだ大量の仕事をやり残している。そのツケを清算せぬままの「日中枢軸」は取り得ない選択だ。
また、中国から見た日本の戦略的価値は、日本が米国を入れたゲームをすることで最大化する。安全保障の面で、特にそれが言える。中国にとって、関係改善がもたらすメリットと関係悪化がもたらすデメリットの差し引き落差が日本ほど大きい国はそうないが、それも米国というゲーム参加者がいればこその話だ。非常に微妙な舵取りだが、中国との関係を改善していくにも、米国の存在は欠かせない。また、中国自身、「米国に背を向けて日中枢軸」という選択には決して応じない。日本が見る影もなく衰退してしまえば別論、そうでないかぎりアジア太平洋では日米中の三極関係は維持されていく。それが国際政治の現実だろう。
その現実の中で日米中の平衡関係を少しずつ動かしていくしかない。中国とのディールで米国を使う、米国とのディールで中国を使う、日本だけでなく米国も中国も同じことをするだろうが、その中で日本の国益をゼロサム・ゲーム式でなく伸張させる、すなわちそれが米・中にとっても利益になるような国益追求の道を探すこと、それを米・中にも説得できる論理を磨くこと、そのために必要な国論の統一、そして以上すべてを継続する努力が求められる。日米中の三角関係は必ずしもゼロサム・ゲームではないのだから、より前向きな、日本という辺が光る三角形を目指していくべきだ。
こうして見ると、道は遠い。でも「できない理由」を並べ立てて終わるのは情けない。いま、アジア通貨統合と唱えても米国は嗤うだろう。一歩ずつブロックを積み上げていくしかない。それに、悲観的な見通しだけでもないのだ。中国はいま、人民元の事実上のドルペッグ制と現行為替レートを固持しながらも、その得失についてずいぶん悩んでいるはずだ。韓国や台湾など他の近隣には、何の発表もないが事実上の円ペッグではないかと思わせる為替レート変動を続けている国・地域がある(グラフ参照)。それが賢明、適切、公平かは今後議論すればよい。著者が本書で明らかにしたように、通貨統合に向かうためのハウツーは欧州の経験でずいぶん勉強できる。
嗤う米国を多少見返せる日がいつ来るか、東アジアの真価はそこで問われることになる。
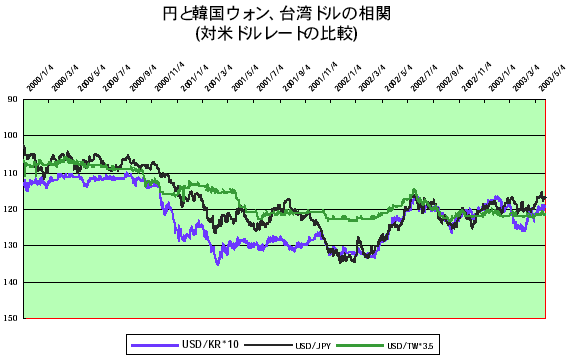
(本稿の簡略版を経産ジャーナル8月号書評欄に掲載)
